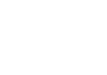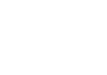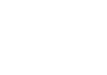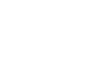重要なお知らせ
表示するお知らせはありません。
シニアの方へ新着情報
-
2024.03.05
-
2024.02.08
-
2023.12.07
-
2023.10.06
-
2023.09.22
情報誌「いのち輝く」
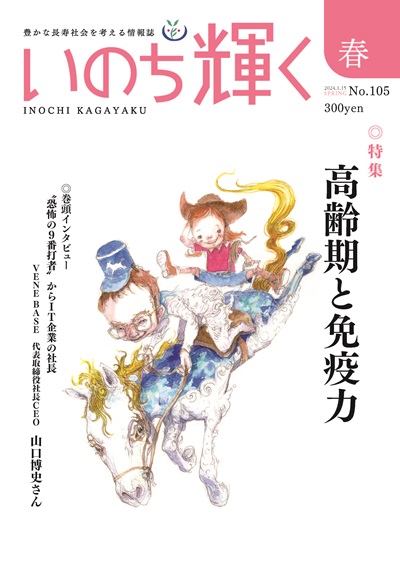
県民のみなさまへ 新着情報
-
2024.03.06
-
2024.01.18
-
2024.01.15
-
2023.12.07
-
2023.10.06